2025年6月24日(火)サンパール荒川において、荒川区民生委員・児童委員協議会主催「令和7年度 第1回 障がい者福祉部全体会」が開催されました。
「精神障がいの基礎知識、対応の仕方等について」というテーマの講演会として、荒川区の民生委員・児童委員協議会障がい者福祉部会 から約 30 名の方が参加されました。
講師として、ソラティオ23から2名、コンパス(荒川区精神障がい者相談支援事業所)から2名、合計4名で登壇させていただきました。
当日傍聴させていただいたので、講演会の様子や内容、傍聴した感想などを前編・後編に渡ってお伝えいたします。
当日のメニュー
- 部会長よりご挨拶
- 精神障がいの基本的知識の説明(15分間)
- 当事者3名によるリカバリーストーリーの紹介(各15分間)
- 登壇者4名のトークセッション(20分間)
- 参加者との質疑応答(10分間)
- 担当地区会長よりご挨拶
精神障がいの基本的知識等の説明や全体的な進行は、コンパス所属の「こさか」が担当させていただきました。
冒頭で参加者とのトークも織り込まれ、精神障がいがある方に対する一般的なイメージとして、以下が挙げられました。
- 距離を感じる
- 接する際に何に気を付けたら良いかわからない
- 人によっては怖いと感じる
精神障がいは基本的に生まれつきのものではなく、人生の途中で発症する中途障がいです。
こさか自身、精神障がいの当事者であり、人生の途中で発症しています。
発症当初は、こさかにも精神障がい者への恐怖感や精神科受診の不安があったことなどが語られました。
先ほどの参加者とのトーク、精神障がいがある方に対する一般的なイメージという伏線がここで回収されたことに「なるほど」と感じる場面でした。
こさかの体験談を少し紹介させていただきます。
精神障がい者への恐怖感や精神科受診の不安がある中で、
こさかは精神科を受診し、デイケアに通うことになります。
そしてその中で、他の精神障がい当事者との出会いを経験します。
この出会いは安心感へとつながり、
さらに当事者同士の支えが
国民スポーツ大会におけるバレーボール、精神障がい者の部への
参加にもつながりました。
こさかが所属していたバレーボールチームは、
埼玉県内で毎年予選敗退するチームだったそうですが、
勝ちたいという気持ちを胸にボールを追いかけ、
厳しい練習を重ねて
埼玉県代表になり、
関東代表になり、
そしてなんと日本一になったそうです。
ドラマみたいなストーリーですね。
その他、鈴鹿サーキットでバイクを走らせるなど、
精神障がいがありながらも当事者との出会いから支え合いを経て、
前を向いて新たな挑戦に挑む経験談に、
会場の皆さんは聞き入っていました。
国内の精神障がいの状況
また、国内の精神障がい者数について、平成29年は420万人でしたが令和7年は600万人という調査結果も紹介されました。
統合失調症、気分障がい、諸々の依存症など、今では精神障がいは特別な病気ではなく、身近な誰もがなり得るものであると語られました。
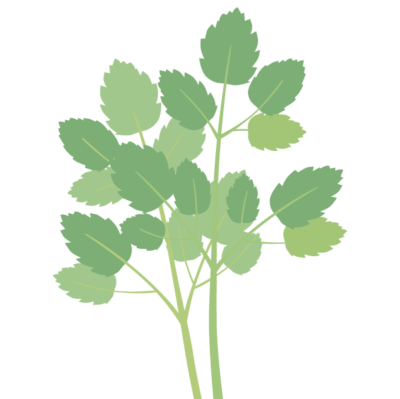
精神障がいの方でも治療を受けている方は基本的には穏やかな方が多く、私自身、精神障がいの方に接する際、特別な配慮はしていないんですよ。
ただ1点大きな特徴は、「目に見えない病気」であり、そのため家族や友人、本人も、何が起きているか理解しづらいということです。

治療につながった場合であっても、精神科通院における診察が5分未満という病院が26.5%、精神障がい者の3.8人に1人は十分な診察を受けていないのではないかといった説明もありました。
その他、精神科の入院患者満足度の調査結果や、本人が同意したうえでの入院かどうか、入院中の隔離や身体拘束等についても説明がありました。
様々な課題が挙がりましたが、一方で精神科には高齢の認知症患者もいらっしゃいますし、これらが病院側だけの問題ではないこと、そして精神科であってもインフォームド・コンセントが大事であることも語られました。
当日参加された皆さんには、人権に最大限配慮した医療の重要性、当事者同士の支えやピアサポートの活用による効果、精神疾患に対する理解促進が大切なことを持ち帰っていただきたい、そんなこさかの気持ちが伝わったのではないかと思います。
前編はここまで。
後編の「リカバリーについて」に続きます。
ぜひ後編もお読みください。
コメント