2025年7月9日(水)、サンパール荒川でシンポジウムを実施いたしました。
令和7年度精神保健医療福祉を当事者とともに考えるシンポジウム
~「良質な精神科医療とは」~
シンポジウムには以下の皆さまにご参画いただきました。
■長瀬 幸弘 先生
医療法人社団東京愛成会高月病院院長(公益社団法人日本精神科病院協会理事)
■鮒田 栄治 先生
都立精神保健福祉センター地域援助医長(精神科医)
■コレット 美喜 氏
一般財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院看護部長(看護師)
■高橋 美久 氏
株式会社MARS 就労継続支援B型事業所TERRA 管理者・ピアサポーター
■厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課担当 佐藤課長補佐
進行は、コンパスのこさかが担当しました。
精神保健医療福祉に関する検討会では、
様々な施策が決定、推進されていますが、
検討会も厚生労働省も、国民にとって非常に遠い存在です。
今回のコンセプトは
「遠い存在の検討会を地域に持ってきてしまおう」
というもので、
精神科医療について分析しつつ、
今後の期待も込めて皆さんと議論したいと考えております。
本日は厚生労働省の他、我が国を代表する方々に来ていただいておりますので、
シンポジウム終了後はぜひ名刺交換をしてください。
そして現場で何か困ったことがあれば、
ぜひ名刺を手に取って連絡をしていただきたいと思っております。
シンポジウムの前に、こさかより精神科医療の現状(精神科外来診療における5分未満診察の割合や入院患者の満足度、身体拘束等)について共有がありました。
前回のブログ「前編「精神障がいの基礎知識、対応の仕方等について」~令和7年度 第1回 荒川区障がい者福祉部全体会~」でも国内の精神障がいの状況について触れているので、ぜひご確認ください。
~シンポジウムのほんの一部をご紹介します~

日本の精神科医療について、ひとりの看護師として、または看護部長として~コレットさん
- 現状として行動制限は存在し、拘束ゼロの日は非常に少ないんです
- 現場では、10数年前と比べて確かに変化はありますが、それでも心が痛み葛藤する場面もあります
- 様々な場面で現場のスタッフが葛藤を持ち続けられること、諦めずに継続することが重要です
- ピアサポーターと協働することで視点が変わり、現場ではとても助けられました
立場を越えて、何でも真摯に向き合って真摯に答えてくれるコレットさん。
今でも諦めずに葛藤されているのだろうなぁと、現場の皆さんに想いを馳せながら聴かせていただきました。

日本精神科病院協会の立場から、現在の精神科医療の状況と課題について~長瀬先生
- 地域によって速度は異なりますが、人口減少に伴い病院数も減少しているので、病院の存続も課題です
- 高齢の方、様々な障がいをお持ちの方がいるため、地域生活を支える工夫も必要で、病院は多様なミッションを抱えながら運営しています
- 地域生活を支えるために外来診療の十分な診察時間や質の向上は重要ですが、医療のパッケージの問題もあり、5分未満の診察が多いのも現状です
精神科医療が直面する複雑な課題を率直にお話いただき、変化への対応の必要性を説いてくださりました。
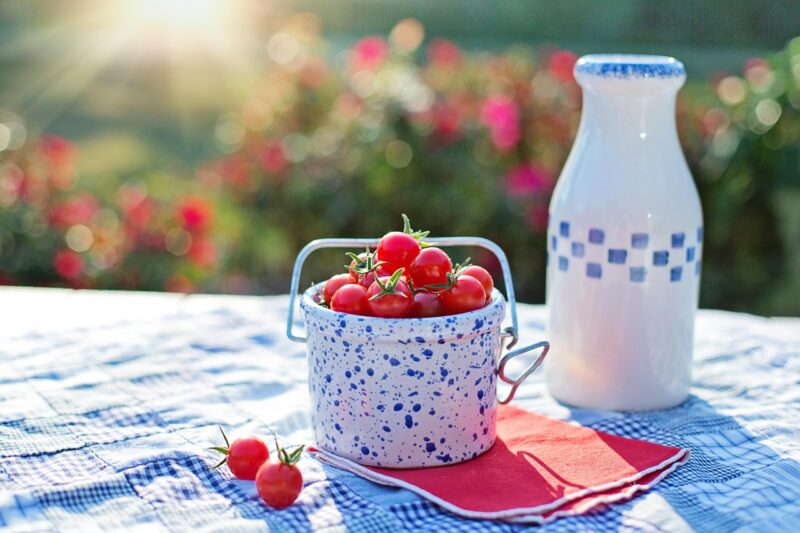
20年の精神科医としてのキャリアを持ち、現在は精神保健福祉センターで訪問(アウトリーチ)も含めて困難事例に向き合う立場から見える精神科医療とは~鮒田先生
- 外来診療とは違い、実際に自宅や地域に何度も訪問することで、本人の立場、家族や周囲との関係性と認識の違い等、様々なことが見えてきます
- 本人はそんなに困っていなくても地域が困っているケースでは様々な主張があり、本人ではなく周囲が入院を望むこともありますが、入院以外の方法も模索しています
- 複雑なケースも多いため多角的な視点が必要で、多くの関係者の協力を得て本人の望む生活について日々検討しています
アウトリーチの効果と地域における支援の複雑さや難しさ、悩みながらも丁寧に本人の意思を尊重するお話が印象的でした

◆厚生労働省 佐藤課長補佐にお伺いしたいこと3点
- 患者の精神科医療に対する満足度等の調査結果について
- 本人非同意の入院について制度のあり方
- 厚生労働省精神障害保健課は精神保健医療福祉政策についてどんな軸で考えているか
質問3点について~ 厚生労働省 佐藤課長補佐
- 満足度の尺度は複雑で多様ですし、病院により受診の予約制度に違いもあり、調査の難しさを感じています
- 本人が困っていない場合は受診に対するハードルがあるので、周囲の困りごとを福祉相談等につなげやすい環境が大切だと考えています
- 精神保健医療福祉政策の軸は、これまで打ち出してきた政策の方向性そのものであり、制度改正をしながら適宜修正していくというのが基本的な考え方です
各質問に対しして率直かつ慎重な回答をいただき、精神科医療の複雑さと改善の難しさをお話しいただきました

【関係者の精神科医療の分析を聞いたうえで、当事者として自由な意見を~高橋さん】
- 外来の受診時は雰囲気等により患者が話しづらい状況がある一方で、患者自身が医師の多忙さに配慮して話せないという現状もあります
- ピアサポーターは本人に近い立場でもあり、医師より時間もあるので、ピアサポーターの活用によって精精神科医療の満足度に効果があるのではないでしょうか
- 福祉におけるピアサポーター関係の加算のように、医療におけるピアサポーターの制度的位置付けにより、活用が促進される社会になると考えています
当事者の視点から精神科医療における外来診察の課題を具体的にご説明くださいました。
ピアサポーターの重要性を改めて感じ、活用促進の課題について考えさせられるお話でした。
その他、会場とのやり取りではシンポジウムを入院患者さんに届けるオンライン配信等についてご意見をいただきました。
今回オンライン配信はありませんでしたが、国の検討会がYouTube配信されるものがあることも紹介されました。
日本を代表する各専門家が、
様々な視点や立場から日本の未来のために
多角的な意見を出し合う国の検討会。
そんな全国レベルの議論を、
地域社会に持ち込んでしまおうという
大胆なコンセプトの本シンポジウムでした。
精神科医療に対するこれまでの軌跡や葛藤、現状と今後の展望など、
国の検討会レベルの議論を
肌で感じていただける機会となったのではないでしょうか。
このシンポジウムを機に、
今までよりちょっと広くて俯瞰的な視点で
精神科医療について考えいただけると、 とても嬉しく思います。
今回も最後までお読みいただきありがとうございます。
コメント