前編はこちら
「精神障がいの基礎知識、対応の仕方等について」というテーマで実施された講演会の後編です。
前編では精神障がいがある方に対する一般的なイメージの共有、進行役の「こさか」の体験談、国内の精神障がいの現状などをお伝えしました。
後編では「リカバリーについて」からお伝えしていきます。
リカバリーについて
本講演会の目玉でもある、登壇者3名によるリカバリーストーリーに向けて、こさかより、リカバリーについての説明がありました。
- リカバリーの概念はアメリカから発症し、今では国内でも重要な概念であること
- リカバリーとは病気を治すことや寛解が目的ではないこと
- 病気があっても自分らしく生活できるようになることや、自分らしく生活できるようになるプロセスも含めて「リカバリー」と言う
そして、リカバリーストーリーを語る3名に敬意を払い、ありのままに受け止めていただき、内容はこの場限りとしていただきたい旨が伝えられました。
※本ブログではリカバリーストーリー自体のご紹介は控えさせていただきます。

リカバリーストーリーを受け取って
人生の途中で今までにない症状や現象に見舞われた時、どんなことを考えるかは人それぞれだと思います。
割とすぐに受診を考える方もいると思いますが、医療につながるまでに辛く長い時間がかかる方もいらっしゃいます。

まさか自分が精神科を受診するなんて・・・
そう思いながらも受診することでやっと診断名が付いて、やっと自分のことが理解できるようになるんです。
それぞれ家族や支援者、当事者の支えがあってリカバリーの道を辿ることや、「リカバリーに終わりはない」という言葉が印象的でした。
また、「家族の後押しがあって就いた計画相談という仕事が好きになってしまい、今では私生活とのメリハリを付けることが課題なんです」とにこやかに話されていたときは、思わずこちらの頬も緩んでしまいました。
当事者・ピアだからこそできる共感的支援、
信頼関係構築のしやすさがある一方、
距離感が曖昧になって感情に流されないよう
注意することが必要なんです。
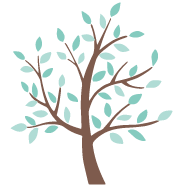
質疑応答
プログラムの最後にある質疑応答では、参加者の経験からこのような場合にどうしたら良いのかといった問いに、こさかが福祉だけでなく医療等との連携も含めて説明のうえ、相談先としてコンパスをご活用いただきたいこともお伝えしました。
傍聴した感想
会場の後ろの席で傍聴していると、参加者の皆さんの背中を見ることができます。
皆さんの背中から、楽しんでいる様子、「なるほど~」と初めて聴く話を受け取っている様子を感じ取ることができます。
例えば、こさかは厚生労働省の検討会に長年参画し、精神障がいにおける政策の実現に寄与していますが、緊張しながらも覚悟を持って奮闘している姿が語られた際は、多くの背中が前のめりになり、感嘆と共に聞き入っている様子が見られました。
こさかやリカバリーストーリーの語り手の言葉が会場の皆さんに届いている様子を感じながら、本講演会のような機会が増えることを願わずにはいられませんでした。
さいごに

人によっては、精神障がいがある方を怖いと感じることもあります。
ある事件やニュースがきっかけで、精神障害全般に対して偏った印象を持ってしまうこともあります。
そんな現実もありますが、
もし、自分や自分の大切な人が精神疾患にかかったらどうでしょうか。
そのイメージは変わりますか・・・?
リカバリーストーリーにあった問いに考えさせられた方は少なくないと思います。
メンタルヘルスの不調は身近な人
誰にでも起きるもの
この言葉が心に染みる講演会でした。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント